���А��i���p��̒��ӓ_
���Ў��ΐ��i�̈�����
�@���А��i�ɑg�ݍ��܂�Ă��鎥�ŁA�i�v���i���Ƀl�I�W�����Γ��j�͑�ϋ��͂ł��B
�s�p�ӂɑ��̎���H��A�S�ЂȂǂ��߂Â���ƁA�w�������܂�Ďv��ʉ�������邱�Ƃ�����܂��B
�戵�ɂ͏\�����ӂ��ĉ������B
�@�܂��A�S���p�y�[�X���[�J�[�����̕��́A�{���i�ɋ߂Â��Ȃ��ʼn������B
�i�v����d���ɋ߂Â��Ă͂����Ȃ�����
�@�ȉ��ɋ�������̂��߂Â���Ǝ�������āA�L�^���ꂽ���e����ꂽ��A�g���Ȃ��Ȃ�Ȃ�
�̏�̌����ɂȂ�܂��B
�E�N���W�b�g�J�[�h��L���b�V���J�[�h�Ȃǂ̎��C�J�[�h�i�ŋ߂͎Ј������C�f�[�^���������܂�Ă��܂��j
�E�A�i���O���̎��v�i���Ԃ��������܂��j
�E�t���b�s�[�f�B�X�N�Ȃǂ̎����L�^�}��
�E�������[�J�[�h�iSD�J�[�h�AUSB���������j
�E�p�\�R���Ȃǂ̐����@�B
���𗘗p����̂ɕK�v�Ȓm���ɂ���
�z����
�@���Ζ{�̂��A�������ċz�����Ă���ꍇ�A���������̂ɕK�v�ȗ͂��z���͂Ƃ����܂��B
�P�ʂ̓L���O����(kgf)�A�O����(gf)�Ƃ��Ă��܂��B
�@�}�O�l�b�g���p�@��̋z���͂̋����́A�\�ʎ������x�Ƌz���ʐςƂ̑g�ݍ��킹�ɂ��܂��B
�z���͂̐ݒ�̓��[�N�ɍ��킹���z���ʐρi��p�ʁj���d�v�ȃ|�C���g�ŁA������̔��A�ގ��A
�z���ʂ̏�ԁA�M���b�v�ɂ���ĕω����܂��B
�@�Ⴆ�Ήi�v����S�Ђɋ߂Â���Ƃ��܂��B�i�v���̕\�ʂ��m�ɑ��Ƃ���ƁA����̓S�Ђ͂r�ɂɂȂ�܂��B
��������ɂ��Ă������Ă���킯�ł��B
�S�Ђ͎��ɂȂ肫���Ă���킯�ł����A���R���ɂȂ肫���ʂ͌��܂��Ă���̂�
����ȏ㋭�����������Ă��Ă��O�a��ԂƂȂ�܂��B
�@�M���b�v�̊Ǘ����d�v�ł��B���ƑΏە��Ƃ̊ԂɃM���b�v������ƁA�ɒ[�Ɏキ�Ȃ�܂��B
������2���ŕω����܂��B
�@�ގ��ɂ���Ă��z���͕͂ω����܂��BSS400��100%�̋z���͂��Ƃ���ƁAS45C�ł�80%���x�ɒቺ���܂��B
�@�Ȃ��d���̏ꍇ�́A�R�C���̔��M������܂��̂ŁA�₦����Ԃł͋z���͂������A
�����Ԓʓd���ĔM���Ȃ�����Ԃł͋z���͂��キ�Ȃ�܂��B

�z���́i�ۖ_����}�̗l�ɒi�X�Ȃ��Ă����j
�z����
�@�z��������̂��A���������������Ď��ɋz��������ꍇ���A�z���͂Ƃ����܂��B
�z���͂���������Ƃ����āA�z���͂������Ƃ͌���܂���B
�@�P�ʂ̓~�����[�g��(�o)�Ƃ��Ă��܂��B
�z���͂Ƌz���͂̃e�X�g���@

�z���͂̑���
�@�z���͂�z���͂��v�Z���ŎZ�o���邱�Ƃ́A��ύ���Ȃ��̂ł��B
�����ŁA���ۂ̂��̂Ɠ����̕���p�ӂ��A���ۂ̃��[�N�ł̃e�X�g�����ɏd�v�ƂȂ�܂��B
���Ђł͊e����̃e�X�g�S���������A�p�r�ɍ��킹�đ��肵�Ă��܂��B�ȉ��Ɉ�ʓI�ȑ�����@���������������܂��B
�z���͂̃e�X�g���@�F�Œ肵���}�O�l�b�g�Ƀ��[�N���z�������āA
�v�b�V���v���X�P�[���Ȃǂň�������A�}�O�l�b�g���烏�[�N�����ꂽ�d�ʒl��ǂ݂܂��B
�z���͂̃e�X�g���@�F�Œ肵���}�O�l�b�g�Ƀ��[�N�����X�ɋ߂Â��Ă����A
���[�N���}�O�l�b�g�ɋz�����ꂽ������ǂ݂܂��B
�@�Ȃ��z���́E�z���͂Ƃ��l�͖ڈ��ł���A�ۏؒl�ł͂���܂���B
���[�N�i�p�S�j
�@���[�N(�p�S)�Ƃ͎������z���͂������S�̂��ƂŁA���C��H���\�����邽�߂̓�S�ł̂��ă��[�N�Ƃ����܂��B
���[�N�͎��ɂ��߂Â����p�������Ă���̂ŁA���C��H�̈ꕔ�Ƃ��Ďg���A���͐��̌o�H�𐧌䂷��d�v�Ȃ��̂ł��B
�@�ޗ��́A��������c�����C�����Ȃǂ̓d���C�I�����̗ǂ����̂��v������邪�A�����œ��萫�̗ǂ��S��(SS400)���g�p����邱�Ƃ������ł��B
���[�N�̎g�p��
�@�Ⴆ�A�Q�̎��ƃ��[�N���g�p�����ꍇ�́A�z���͂Ƌz���͂̊W�͂����悻���̂悤�ɂȂ�܂��B

�E�[�̐}�̂悤�ɁA���ΒP�̂̏�Ԃł͂m�ɂ���r�ɂɂR�U�O�x�S���ɓn���Ď��͐�������܂��B �����Œ����̐}�̂悤�ɁA���̗��[�Ƀ��[�N���z��������ƁA�S�����܂���Ă������͐��� ���[�N�̒[�Ɏ��͂��W�����܂��B���[�̐}�́A���[�N������ɂP����������Ԃł��B ���̂悤�ɁA���͐��̗����ς��邱�Ƃ����[�N�̖����Ȃ̂ł��B
�@���̂悤�ɁA���[�N���g�����̎��̎����Ă���m�ɂƂr�ɂ��߂Â����艓��������A ���͂��o��������ς���悤�ɑg�ݍ��킹�A�z���͂��邢�͋z���͂傳����悤�ɉ��p�ł���̂ł��B
�Z��
�@���̎����Ă��鎥�͐��́A�m�ɂ���r�ɂɂ�����̕�������`���Ă��܂��B ���̎��͐���S�Ȃǂɂ���ĖW����ƁA���̔\�͂͋ɒ[�ɒቺ���܂��B ���̔\�͂��ő���ɔ��������邽�߂ɂ́A���͐��̒Z���ɒ��ӂ��Ȃ���Ȃ�܂���B
���͐�
�@���͂��m�ɂ���r�ɂɌ������Ăǂ̂悤�ɏo�Ă��邩��`�������̂��ƂŁA���ʂ͖ڂɌ����܂���B �R���p�X���g���Ǝ��͐��̌����A���S�Ȃǂ𗘗p����Ǝ��͐����o�Ă���l�q�����邱�Ƃ��o���܂��B
���E
�@���͂̉e�����y��ł����Ԃ̂��ƂŎ���Ƃ������܂��B �����̂��̂����������Ƃ��ɂ́A���E�������܂ŋy�ԕK�v������܂��B
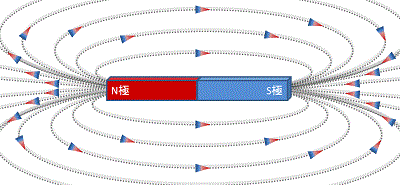
��ʓI�Ȗ_���̎��͐��Ǝ��E
�@���Ђł͒��N�̃m�E�n�E�ɂ��A�m�ɂr�ɂ����܂��g�ݍ��킹�āA���E�͈̔͂��R���g���[�����Ă��܂��B
�@�Ȃ��A�}�O�l�b�g���p�@�����ׂĎg�p����ꍇ�́A���݂��̎��E�ɉe�����o�Ȃ��悤��
�Ԋu��z��Ȃǂ��H�v����K�v���łĂ��܂��B
�\�ʎ������x
�@�\�ʎ������x(�K�E�X/�e�X��)�Ƃ́A������͈̔͂ɂǂꂾ���̎��������邩��\���P�ʂł��B
�i�K�E�X�F1�����Z���`���[�g�� �^ �e�X���F1�������[�g���j
�����Ƃ͎��͐��̑��̂��ƂŁA�������x�Ƃ͒P�ʖʐϓ�����̎��E�̋�����\���܂��B
�@���̒l���傫���قǎ��͂������Ȃ�܂����A�}�O�l�b�g���p�@��̏ꍇ�A
�������x��������(�C�R�[��)���\�������Ƃ͌�����܂���B
�E�s(�e�X��)�F���ےP�ʌn�iSI�P�ʌn�j
�E�f(�K�E�X)�F�Z���`���[�g���E�O�����E�b�P�ʌn�iCGS�P�ʌn�j
�\�ʎ������x�̑���
�@�P�̃}�O�l�b�g�̎������x�̓}�O�l�b�g��p�ʂ̕\�ʂő��肵�܂��B
���u�Ƃ��đ��肷��ꍇ�́A�@�\���ʂ����ӏ��ł̑��肪�d�v�ɂȂ�܂��B
����̓e�X�����[�^�[�i�K�E�X���[�^�[�j��p���čs���܂��B
�@���肷����ɂ���Ă͈قȂ錋�ʂ邱�Ƃ�����̂ŁA������̈ʒu��M���b�v�Ȃǂ�
���L����K�v������܂��B
�������x�̒P�ʁA�K�E�X�ƃe�X��
�@���C�̒P�ʂɂ�����SI�P�ʌn��e�X����ł͒ʏ�g�p����l�ɑ��đ傫������ׁACGS�P�ʌn��K�E�X���p���鎖�����X����܂��B
�@���Ђł͕X��CGS�P�ʌn��K�E�X���W���Ƃ��Ă���܂��B
| �P�ʑ����\ | ||
| G�i�K�E�X�j | T�i�e�X���j | |
| 0.01G | 1��T | 0.000001T |
| 0.1G | 10��T | 0.00001T |
| 1G | 100��T | 0.0001T |
| 10G | 1mT | 0.001T |
| 100G | 10mT | 0.01T |
| 1000G | 100mT | 0.1T |
| 10000G | 1000mT | 1T |
�ێ��́iHc�j
�@���̒l���傫���قǎ��͂��ʂ��ɂ����A�������قnj������₷���Ȃ�܂��B
�i�P�ʁF�`�^���A�n��(�G���X�e�b�h)�j
�ő�G�l���M�[�� (BH)max.
�@�c���������x(Br)�ƕێ���(Hc)�̐ςŁABr��Hc����т���(BH) max.���傫���قǁA
���肵���ǂ����ƌ����܂��B
�i�P�ʁF���i�^���R�A�l�f�n���j
�L�����[�_�i���j
�@���̎c���������x���O�ɂȂ鉷�x�ł��B�L�����[���x�Ƃ��Ă�܂��B
���̉��x���㏸����ɔ����A���ꂼ��̎�����ł̎����͌������Ă����A�L�����[���x�ȏ�ł͎c���������x���O�ɂȂ�܂��B������E����ԂɂȂ�܂��B
�@�L�����[�_�͎��̎�ނɂ���ĈقȂ�A�t�F���C�g���̏ꍇ�A��460�����L�����[�_�ɂȂ�܂��B
���ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A�L�����[�_�܂Ŏ��Ƃ��Ďg����킯�ł͂Ȃ��A���g�p���x�͂����ƒႢ�Ƃ������Ƃł��B
���g�p���x�̓t���C�g���Ŗ�90���ߕӂƂȂ�܂��B����ȏ�͌��������傫���Ȃ�A�L�����[�_�Ŏ������x���O�ɂȂ�܂��B
�@�܂��A�L�����[�_�ɒB���Ď��͂��������������A�Ăя퉷�ɖ߂��Ă��i���x�������牺���Ă��j���͂��������邱�Ƃ͂���܂���B
�t�����X�̕����w�� �s�G�[���E�L�����[�iPierre Curie�j�������������Ƃ���u�L�����[�_�v�ƂȂ�܂����B
���̎�ނƃL�����[�_
���͍ގ��ɂ���Ĉ���������������A������ނ̎��ł��O���[�h�ɂ���ĈقȂ�܂��B �����ł͑�\�I�Ȏ��̎g�p���E���x�����Љ�܂��B
| ���̎�� | �L�����[�_ | �g�p���E���x |
| �t�F���C�g���� | 460 | 90��1 |
| �l�I�W������ | 310 | 80 |
| �l�I�W������(�ϔM) | 400 | 200��2 |
| �T�}���E���R�o���g���� | 750 | 300 |
| �A���j�R���� | 860 | 450 |
��1�ቷ��ł̌����ɂ��Ă����ӂ��K�v
��2���̌��݂������ꍇ�͕ʓr�l�����K�v
�\�̐��l�͂����܂ł��ڈ��ł���A�����̐��l��ۏ�����̂ł͂������܂���B
�������i�ʁj
�@�������Ƃ́A���̎����̗l�q��\�������萔�̂��ƂŁA�������x�Ǝ���̋����Ƃ̔�ɂȂ�܂��B
�܂莥�̎��C�I������\���ړx���A�������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�u�����ւ̎����̒ʂ�₷���v�̂ق����s���Ƃ��邩������܂���B
�@�킩��₷���������u�S�v�ł��B�u�S�v�Ƃ��������́A���Ɏ������₷�������ł��B
�i���Ɉ������镨���̂��Ƃ��������̂Ƃ����܂��j
�������͎̂������₷���̂ŁA�������̒l�������Ȃ�܂��B
�@���̂悤�ɁA�������̒l�������قǎ��C��R���������������₷���Ȃ�܂��B
�������₷�����ʁA���������₷���Ȃ�܂��B�܂莥�͂��c��ɂ����A���͂������₷���A�Ƃ������Ƃł��B
�t�ɓ��������Ⴂ�قǎ������ɂ����A�������ɂ����Ȃ�܂��B
�������ɂ�������ɂ����قǁA�������̒l�͒Ⴍ�Ȃ��Ă����Ƃ����킯�ł��B
�@���Ƀp�[�}���C(Permalloy)�́A���������̑傫�����Ƃ�ړI�ɍ��ꂽ�S�E�j�b�P��(Fe-Ni)�̍����ł��B